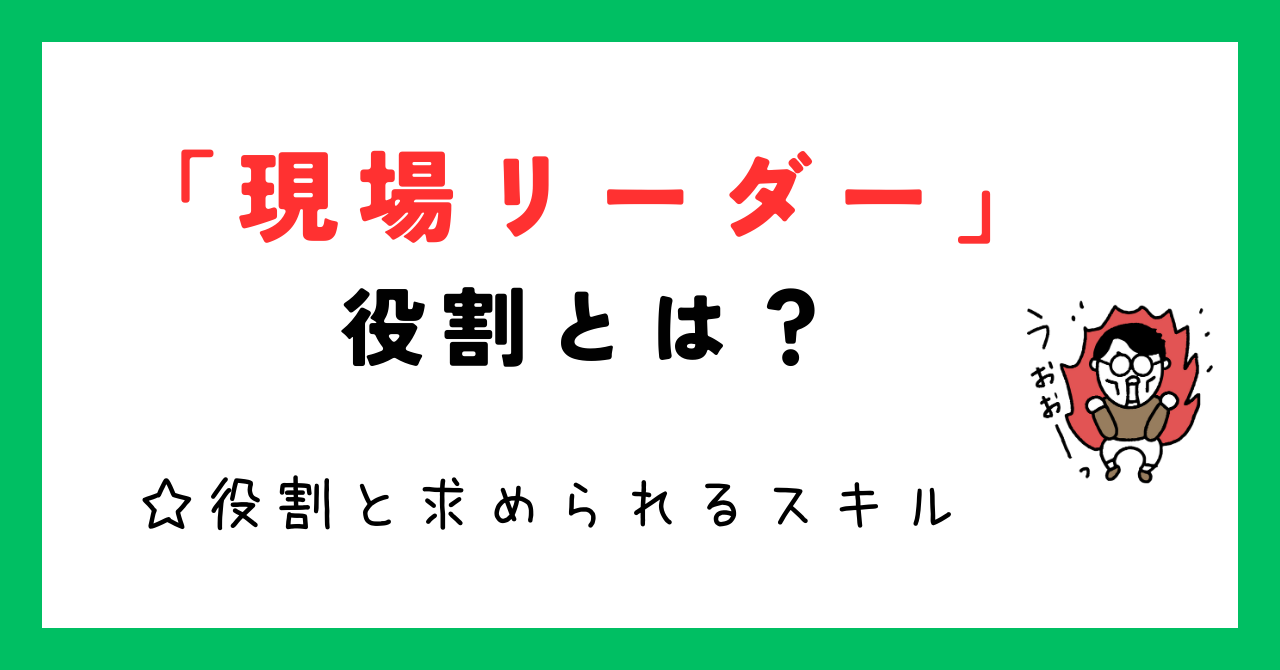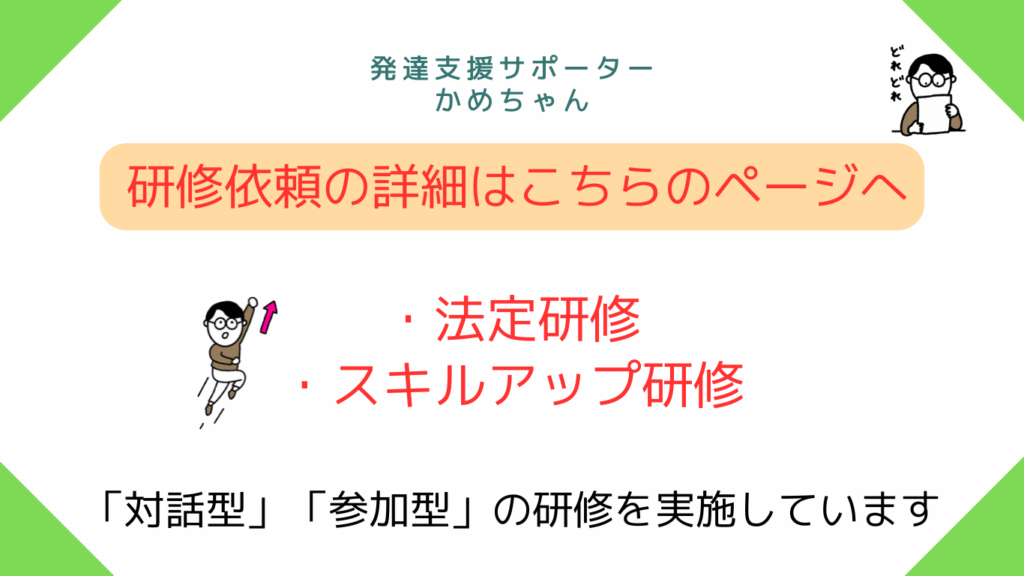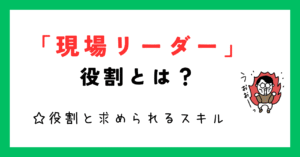日々の支援において
「現場を統括する職員」
の養成はとても重要です。
管理者が不在の場合や
何かイレギュラーな事態が起きた際に
支援を安全に円滑に進めるためには
この「現場リーダー」としてのスキルを
より多くの職員が知っておくことが必要です。
一緒に考えましょう!
目次
放課後等デイサービスにおける「現場リーダー」の主な役割
1. 現場全体の進行管理
- 支援スケジュールを把握し、滞りなく進める。(活動内容、休憩、送迎時間など)
- 突発的な状況への判断・対応。(遅刻・早退・トラブルなど)
- 活動時間中の全体の流れや空気を「俯瞰して見る」役割。
2. 職員間の連携調整
- 他職員の配置や動きを把握・指示する(例:「Aさんはこの子のフォローに入ってください」など)。
- 経験が浅い職員やパート職員のフォローやサポート。
- 支援後の振り返りやフィードバックのまとめ。
3. 子ども一人ひとりの状態把握と支援の調整
- 支援中の子どもの様子を見て、声かけや環境調整を行う。
- 「この子には今日は無理せず負荷を減らそう」など、柔軟な判断が求められる。
4. トラブルや問題行動への初期対応
- 子ども同士のトラブルや突発的な行動に対して、場を落ち着かせる介入を行う。
- 状況によって他職員への応援要請や役割変更を判断。
- 冷静に全体を見ながら「優先順位をつけて動く」スキルが必要。
5. 支援の「質」を守る役割
- 支援計画に基づいた活動になっているかを意識しながら進行。
- 子どもとの関わり方や環境設定が適切かをチェック・修正。
- 「利用中は常に支援の時間だ」と、職員が意識を保つためのリード。
6. 後輩育成・チーム作り
- 支援中のちょっとしたアドバイス。(声かけの例、介入タイミングなど)
- 支援後のミーティングでの振り返りや良かった点・改善点の共有。
- チーム全体の雰囲気づくりや安心感のあるリーダーシップ。
求められるスキル・姿勢
- 冷静な状況判断力
- 柔軟な対応力と優先順位付け
- 職員や子どもとの信頼関係
- 支援理念の共有・実践
- コミュニケーション力(伝える力、聞く力)
現場ではいわゆる
「管理者」や「児発管」ではない職員でも
このようなリーダーシップを自然と担っている人が多くいるかと思います。
逆に、明確な「リーダー不在」の状態だと、支援の空気が乱れたり、対応が後手に回ったりしがちです。
それぞれが自然に取り組めている事柄も
こうして言語化することで、本人の意識を高めたり次を担う職員にとっての道標となります。
まとめ
今回は「現場リーダー」について考えてみました。
支援はチームで取り組むべきもので
そこに関しては職員同士の優劣はありません。
ですが、「全体を把握し、必要な調整をする」という役割の職員は必ず必要です。
リーダーの存在は、支援の「質」と「安全」の両方に深く関わっています。
現場で意見が衝突した際には、一旦リーダーの意見を通しながら
支援終了後に振り返りを行いましょう。
リーダーの意見が「絶対の正解」にならないよう、対話を重ねながら支援の環境を整えていくことがとても大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
あわせて読みたい

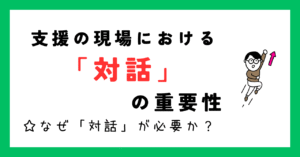
支援の現場での「対話」とは? 放課後等デイサービス
支援の現場において「対話」のスキルは必須だと思っています。 「あの子への声掛けはあれでよかったのか?」「あの人のあの関わりはどういう意図だったんだろう?」 な…