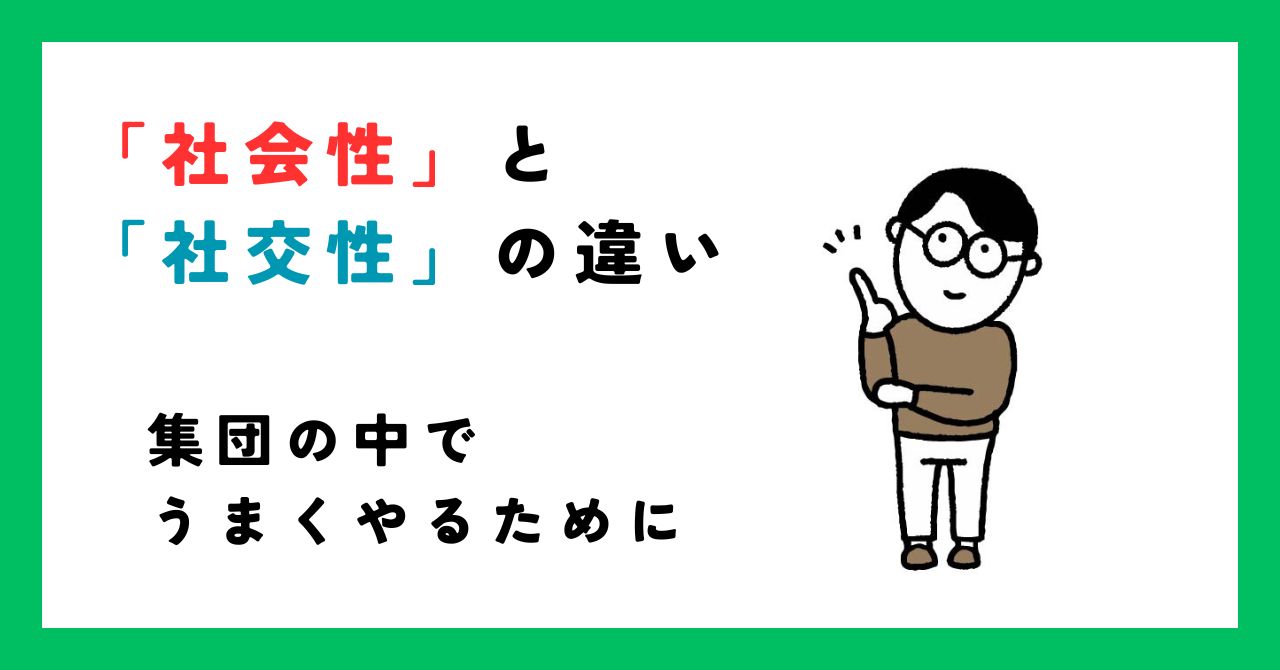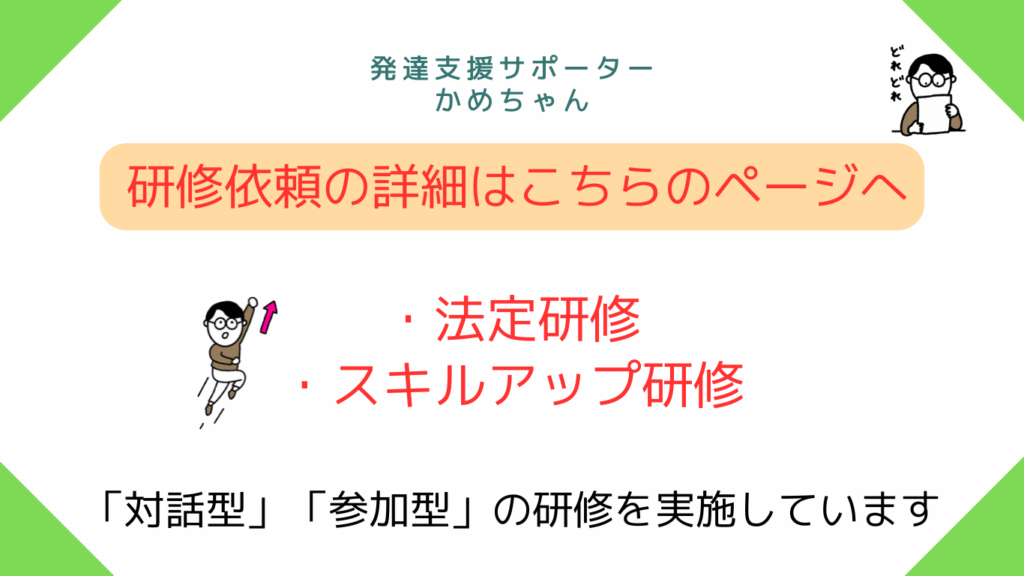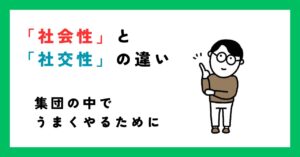今回は「社会性」と「社交性」の違いについて理解をするために書いていきます。
こんな場面をイメージしてみてください。

お友達が「一緒に遊ぼ」って言ってくれてるよ。遊んでおいでよ。
子ども「一緒に遊ぶの嫌だ」
なんで嫌なの?せっかく誘ってくれてるのに〜
誘われた子が「一緒に遊ぶのは嫌だ」と言ったのですが「せっかく誘ってくれたのに〜」と返しています。
この支援者の声掛けは「社会性」「社交性」どちらを大事にしているでしょうか?
それでは一緒に考えていきましょう!!
「社交性」とは?
この支援者の声掛けは「社会性」よりも「社交性」を大事にしています。
もちろん「お友達と遊んでほしい」という気持ちがダメなわけではありません。
ただ、「お友達と上手に遊べることが子どもにとって一番良いことだ」というわけではないはずです。
生きていく上で決して「社交的であるべきだ」ということはありません。
休み時間は一人で過ごす。
休日は一人で過ごす。
行きたくない飲み会には無理には行かない。
などなど、親しくしたいと思わない相手に対して無理やり合わせることを教える必要はないでしょう。
・他者と積極的にコミュニケーションを取ったり、友好的な関係を築いたりする能力や意欲の事。
・会話のスキルや、人間関係を円滑にするための態度などを含む。
・人と話すのが好きで、新しい人と出会うのを楽しむ性格も社交性に関連する。
社交性をざっくりと言い換えるのなら
『相手に好感を持ってもらうための能力』
かなーと考えます。
「社会性」とは?
では、支援の場で大事にしたい「社会性」との違いはなんでしょうか。
・個人が社会の一員として適応し、他者と協力し、集団や社会全体の中で有効に機能する能力や態度の事。
・共同体のルールや価値観を理解し、それに従って行動する能力を含む。
・チームでの協力、公共のルールを守ること、他者の意見を尊重することなどが含まれる。
上記の説明の通り、社会性とはざっくり言うと
『集団の中でうまくやっていく能力』
だと考えます。
この「うまくやっていく」と言う表現が非常に抽象的でわかりにくいですね。すみません。
次で具体的に例を見ていきましょう!
支援の場で伸ばしたい「社会性」
それでは最初の声掛けの例に戻ってみましょう。



お友達が「一緒に遊ぼ」って言ってくれてるよ。遊んでおいでよ。
なんで嫌なの?せっかく誘ってくれてるのに〜
ここで社会性を重視するなら次のようにしてみます。



そっか、一緒に遊ぶの嫌なんだね。
何で嫌か教えてくれる?
一緒に遊べないことをお友達に伝えに行こっか!
このように、社交性よりも社会性を重視して支援をします。
・できない理由を相手に伝える。
・相手が傷付かない言い方、表現の仕方を用いる。
遊びに誘われて断るパターンでは、相手に理由を伝える際に「あなたと遊ぶの楽しくないから嫌だ」とストレートに言ってしまうと集団の中ではうまくやっていけません。
なので相手のことを言うよりは、「一緒に遊ぶより、一人でブロック遊びをしたいから遊べません。」と自分の状況を伝えるようにすると良いです。
「誘ってくれてありがとう」という言葉も使えると、より良いかなと思います。
このスキルは「社交性」ではなく「社会性」、つまり集団の中でうまくやっていくためのものです。
中高生の支援になると、「自分はこういう状況が特に苦手だ」という自己理解が進んでくるかと思います。
社会人になって「飲み会を断る」というスキルも大事な社会性です。
理由を伝えながら上司や同僚を傷つけないように言葉を用いる練習が必要です。



誘っていただいてとても嬉しいです。ただ、大人数での食事がとても苦手で、体調にも影響することがあります。申し訳ないですが遠慮させてください。
こんな断り方であれば「おうおう、それは全然構わんよ」となって欲しいですね。
まとめ
「社会性」と「社交性」の違いについて考えてみました。
そもそも対人コミュニケーションが苦手だったり、集団の場が苦手な子に対してはしっかりとこの「社会性」という能力を一種の「技」として理解して使えるように支援することが大切だなと感じます。
自身の感情をそのまま表現してしまうと不意に相手を傷つけてしまうこともあるため、「うまくやる術」を身につけられると良いです。
ただ、矛盾するようですが、「うまくやれないこと」も当然あります。
ですので、少しずつ自己理解を深めていき自身の苦手を事前に相手に伝えるということも大事になります。



場の空気を読むのが苦手なので、的外れなことを言うことがあるかもしれません。その時は教えてもらえると助かります。
こんなふうに、誰しも苦手があるのは当然です。
それを伝えてお互いに理解し合えるような環境や、社会を作っていけると良いなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!