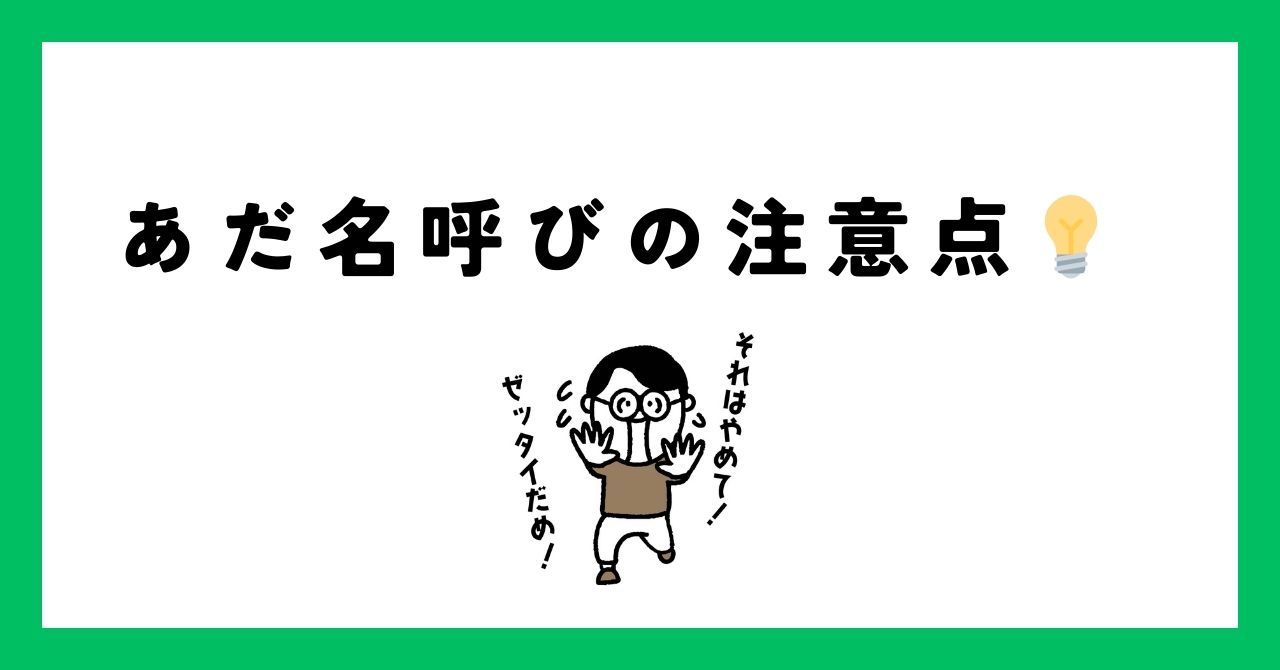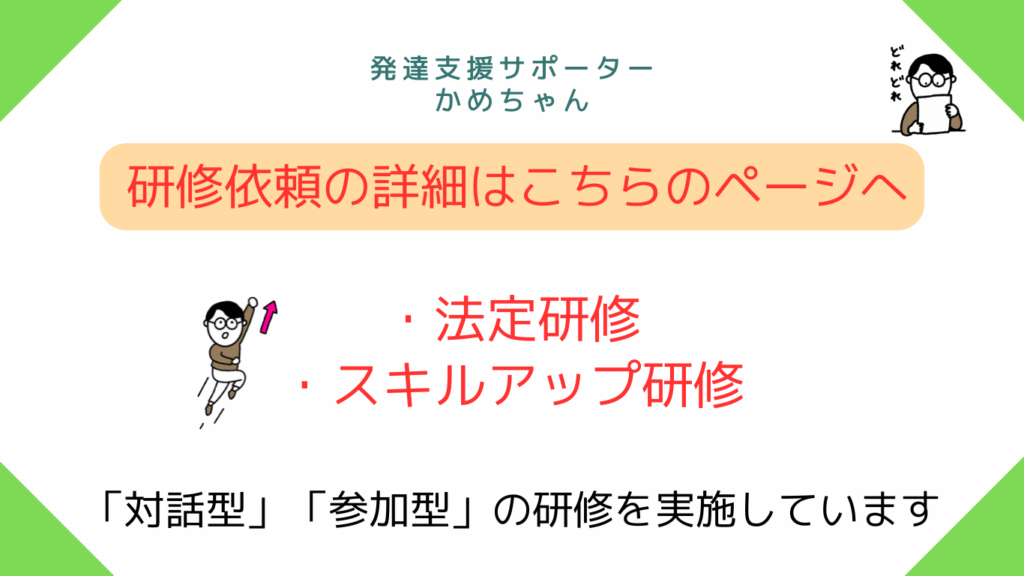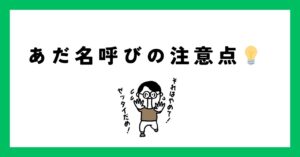皆さんの放課後等デイサービスでは
子どもが職員のことを呼ぶ際のルールはあるでしょうか。
「〇〇先生」で統一しているところもあるでしょうし、「〇〇ちゃん」「〇〇っぴー」など愛称で呼んでもらっているところもあるかと思います。
今回の記事では、愛称で呼ぶ際に注意したい点を書いていきますので最後まで呼んでいただけると嬉しいです。
「呼ばせ方」のルールに妥当性があるか
子どもが職員を呼ぶ時に
「〇〇先生と呼ぶように」
とルールを決めている場合は
そのルールに「妥当性」があるかどうかがとても重要です。
こういった場面に遭遇したことはないでしょうか?

変な呼び方しないの!〇〇先生って呼びなさい!
「先生」と呼ばせることになんら反対はありませんが、子どもから
「なんで『先生』って呼ばないといけないの?」
と聞かれた際には、しっかりと答えられるようにしなければなりません。
です。
職員の思う「当たり前でしょ」や「そういう決まりなの」は理由になりません。
子どもが納得できる妥当性のある理由を用意するようにしましょう。
「目上の人には〇〇さんとか、〇〇先生ってつけないと失礼になるんだよ」
など、どんなルールにも意味があります。
ルールを守ってほしい際にはその「意味」を説明できるように職員間で共通の理解を持つことが大切です。
ルールの意味を職員間で考えた際に
「うまく説明できる理由がないぞ」となるのであればそのルール自体が適切かどうかを疑うようにしましょう。
僕自身は「先生」って呼ばれるのが小っ恥ずかしいので、「かめちゃん」と呼ばれることが多いです。
愛称で呼んでもいい場合のルール決め
小学校の先生などでも愛称(ニックネーム)で呼んでもいいルールにしている方もおられますよね。
放デイでも「〇〇先生」と呼び方を決めずに、ニックネームで呼ぶ場合もあるかと思います。
その中でも子ども達に伝えるルールが必要になってきます。
大事にしたいポイントを2つお伝えします。
愛称で呼ぶ際には上記の2つを必ず守るように子ども達に伝えています。
まず①ですが、呼ばれた相手が不快になる呼び方は当然ながらNGです。



かめのすけって呼ばれるのは嫌だな〜
相手の気持ちが一番なので、その人が嫌がるのであれば他の呼び方に変えるように促します。
子ども同士のパワーバランスで、一方的に我慢をさせないためにも普段からの子ども同士の関わりは注意深く観察する必要があります。
そして②がとても大事なポイントです。
双方の間で了解を得ていても、それを聞いた周りの人が不快になる呼び方はNGです。
差別的な言葉であったり、下ネタ関係であったりと例としては色々ありますが、愛称で呼ぶ際にはこの②もしっかりと伝えます。
まとめ
今回は「呼ばせ方のルールについて」お伝えしました。
一番のポイントは「理由無くしてルールなし」という部分です。
一律に「〇〇先生って呼びなさい」と決めている場合は、なぜそうしなければならないのかの理由も合わせて子ども達に伝えられるようにしてほしいなと思います。
愛称に関しては子ども同士での関係づくりにも関わってきますので、明確なルールを決められるといいですね。
モラルが大きく問われるようになった時代ですので
の使い分けというのも支援者としても学んでいかないといけない課題だなと感じています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ルールから外れることを認める という記事もぜひお読みください