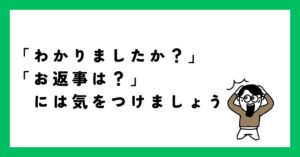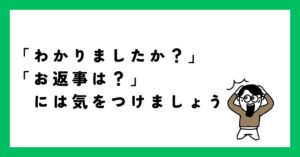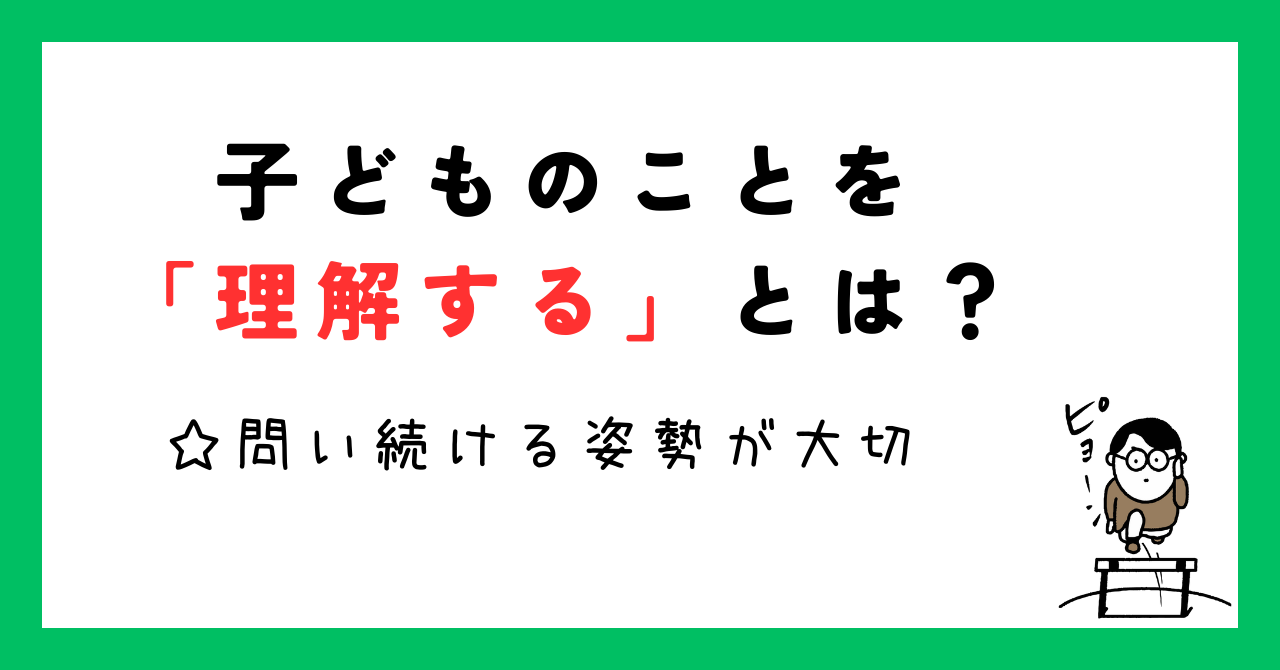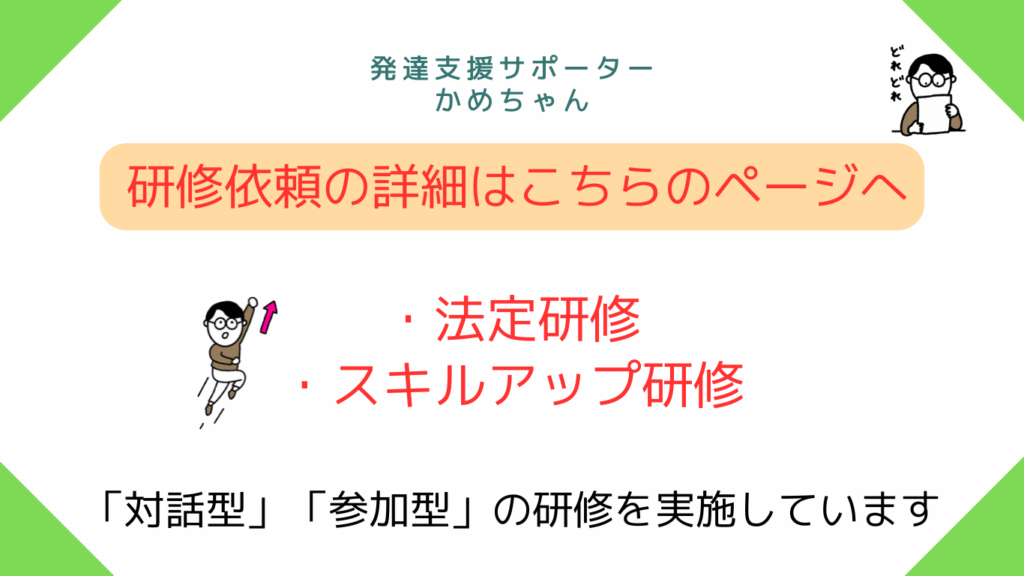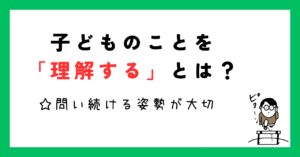〈子どものことを理解する〉
とはどういうことでしょうか。
その子のことを理解して支援をしましょう
と言葉で言うのは簡単ですが
日々支援に携わっているとこれほど難しいことはないなと感じます。

「この子はこういうタイプだから」
「きっとまたこうなるだろう」
このように支援者としては
子どもの行動や反応にある程度の
「予測」や「見立て」をもって関わることがよくあります。
それは支援において大切な視点である一方で、気をつけなければいけないことがあります。
それが「理解したつもりになること」です。
支援の現場でも、さらには職場内での人間関係においてもとても大切な視点ですのでぜひ一緒に考えていきましょう!!
「わかってるつもり」の危うさ
支援者として経験を重ねるほど子どもの行動に対して
「ああ、こういうケースはよくある」
「たぶんこういう理由があるのでは」と見立てを立てられるようになります。
しかし、その見立てがいつの間にか「決めつけ」になっていないか、自問することが必要です。
・すぐに動き回る子に「衝動的な子」とラベルを貼っていないか
・言葉が少ない子に「コミュニケーションが苦手」と決めつけていないか
・反抗的な態度を「問題行動」と片付けていないか
一度「わかったつもり」になると
今、目の前の子どもが発しているサインに
気づきにくくなってしまいます。
支援者の思い込みとその影響
例えば、お昼ご飯の準備の時間になるとイライラする子がいるとします。
「あの子はいつもこの時間はイライラするよね」
「お昼ご飯の準備が嫌なんだね」
とその子の行動の意味を理解したつもりになると
本来必要な支援を見落としてしまいます。



イライラする理由は常に同じじゃないかもしれない
イライラの度合いはいつも違うかもしれない
なぜそうなっているのか?
どんな背景が考えられるか?
と言うことを支援者チームとして常に考える必要があります。
理解とは?「問い続ける姿勢」
本当の理解とは、「わかったつもり」になることではありません。
子どものことを理解するとは
「今この子は、何を感じているのだろう?」
と問い続けることです。
理解とは、ラベルを貼ることではなく
ラベルを外していく作業だなと思います。
・なぜ今、この行動を選んだのか?
・その言葉の背景には、どんな思いがあるのか?
・今日のこの子のコンディションはどうだろう?
その子の行動の 意味 を知ろうとする姿勢が、理解への第一歩です。
そしてその「まなざし」こそが、子どもにとっての安心と信頼の土台になります。



「なんでこの行動をしたのだろう?」
「なんでこの発言をしたのだろう?」
「なんで怒っているんだろう?」
子どもは日々成長しています。
時には少し後戻りをしながら、また成長することもあるでしょう。
つまり、常に同じ場所にはいないと言うことです。
体調を含めた本人の状態や家庭の状況、さまざまなことが影響し合って今があります。
前を向きながら問い続ける姿勢が大切です。
支援者に必要なスキル
では、「理解したつもり」にならないために
支援者として必要なことは何でしょうか。
- 日々の関わりをリセットできる勇気をもつ
昨日のその子と、今日のその子は違います。
前回の関わりを一度脇に置き
今日のまっさらな目で見る意識をもちましょう。 - 言葉だけで判断しない
「やりたくない」と言った裏には
「失敗が怖い」
「やり方がわからない」
といった気持ちが隠れていることもあります。 - わからないことを「わからない」と認める
すぐに答えを出そうとせず
「何があったんだろうね」
「一緒に考えようか」
と子どもと並んで歩く姿勢を大切にします。
まとめ
子どもと関わる仕事は、毎日が「わからないこと」だらけです。
でも、それでいいと思っています。
「わからないからこそ、問い続けられる」ことが
支援者に求められる姿勢だと思います。
理解したつもりになるのではなく、理解しようとし続ける。
その姿勢が、子どもとの関係を作っていき、より良い支援を生むのではないかなと思います。
子どもたちが「私は私でいいんだ」と思えるように
その時のその子の姿をまずは受け止めてあげて欲しいなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!!