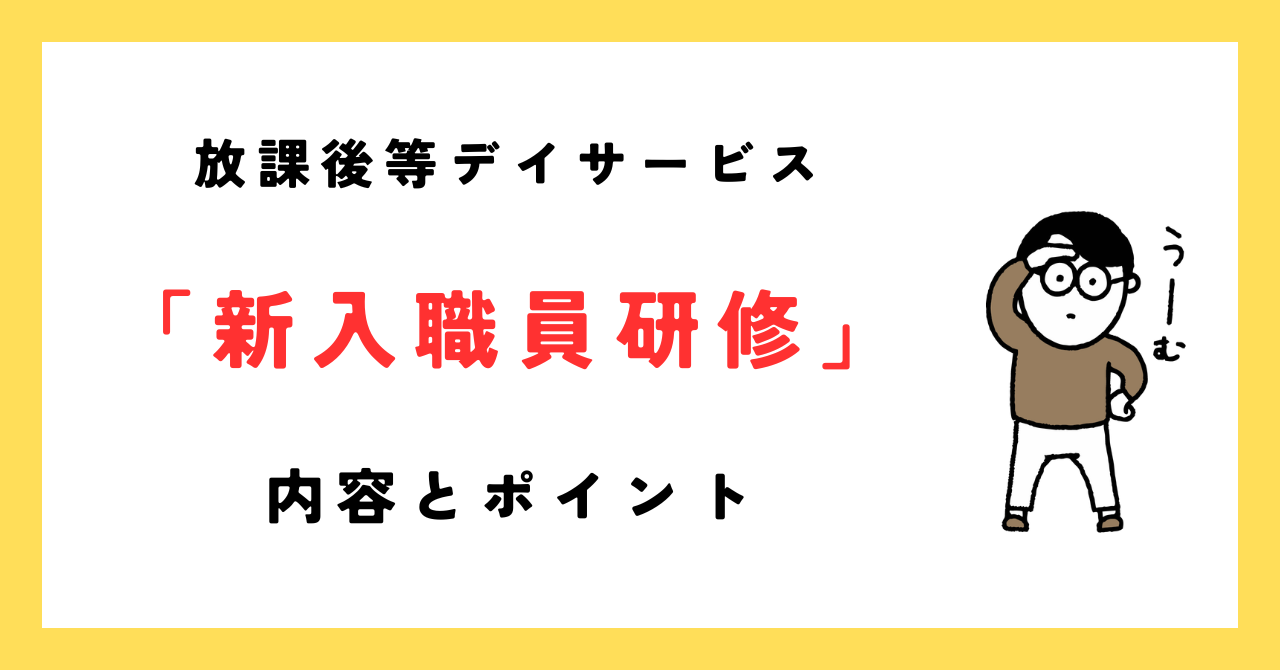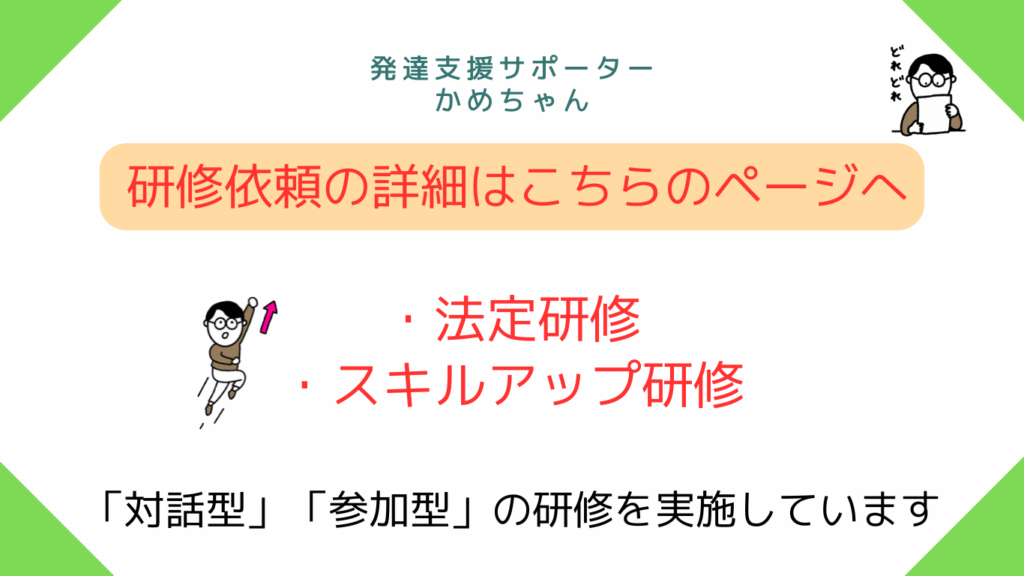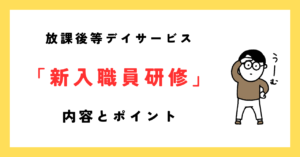今回は放デイにおける「新入職員研修」の内容やポイントについて考えていきます。
配置基準においては「児童指導員」という任用資格が必要ですが、その他加算取得を見込まないのであれば「無資格者」や「未経験者」でも働くことのできるのが放課後等デイサービスです。
資格者であっても無資格者であっても、経験を多く積んでいても未経験でも、1人の職員であることは変わりありません。
事業所として大切にしている思いに対して共通の理解を持つことと、職員同士の対話の土壌を作るということを早い段階で伝えられるといいなと思います。
以下重要度の高い内容で並べてみました。
一緒に考えていきましょう!!
①「理念」と「支援の方針」の共有
まずは事業所(法人)の「理念」の共有です。
一番核となる部分ですので、解釈の相違が起こらないようにします。
次に事業所としての「支援の方針」の共有です。
では「支援の方針」とは一体どういう物でしょうか。
事業所が掲げる理念を実現するためにどのような方法を取るのか
それらを具体的に示すもの
一つ例を考えてみます
【理念】
すべての子どもが自分らしく生きていくために行動する
【支援の方針】
・子ども一人一人の主体性を尊重し、その子のペースを大切にする
・個別具体的な支援を組み立て、子ども一人一人の成長をサポートする
・安心、安全な居場所として環境を調整し創っていく
・その子を取り巻く周囲の環境(家族や学校等)に対しても包括的にサポートする
こうした支援の方針に関して、それぞれの項目をより具体的に表現する文章があるといいなと思います。
入職時にはそれらを確認して常に全職員が共通の理解を持つようにします。
②事業所の「強み」への理解
事業所それぞれで強みがあります。
例えば
先ほど考えた「理念」と「支援の方針」を実現するためのプログラムが上記のような「事業所の強み」です。
「事業所の強み」を理解した上でそれらに関する研修に取り組むようにします。
新入職員の研修ではこの「強み」に関しての基本的なスキルや考え方、それらのプログラムの立て方などを学ぶ機会として設定するといいかなと思います。
③「対話」の必要性について
「理念」「支援の方針」「事業所の強み」が共有できたからといって
その後は自動的に支援の質が向上し続けるわけではありません。

対人支援においては
「職員同士の対話」というものが必要不可欠です。
それはつまり「支援において正解はない」ということが前提にあるからだと考えます。
目的地が共有されていても
そこに走っていくのか歩いていくのかというスピード感だったり
紙の地図を使うのかデジタルの地図を使うのかという手法の違いだったり
が支援者それぞれで微妙に異なります。
④法令により定められている研修
入職時に必要な研修は以下のとおりです。
| ①虐待防止研修 | ※入職時実施 |
| ②身体拘束等適正化研修 | ※入職時実施 |
| ③感染症及び食中毒の予防及び まん延の防止のための研修・訓練 | ※入職時実施 |
| ④感染症BCPに係る研修 | ※入職時実施 |
| ⑤自然災害BCPに係る研修 | ※入職時実施 |
法廷研修に関しては以下の記事にまとめていますのでご確認ください。
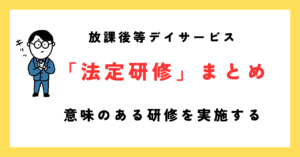
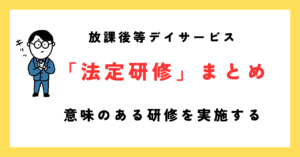
その他 研修案
これまでにあげた内容プラス以下のような研修にも取り組めるといいかと思います。
まとめ
今回は新入職員研修について考えました。
冒頭でも述べたとおり
資格者であっても無資格者であっても
経験を多く積んでいても未経験でも
1人の職員であることは変わりありません。
何よりも大切なことは、すべての職員が「同じ方向を向いて支援に携わっていること」です。
職員それぞれの知識や経験、支援の考え方が違っていても、「同じ方向を向く」ということを大切にしながら日々対話を重ね、より良い支援を提供できるように努力することが求められます。
研修事業にも取り組んでいますので、ご質問やご依頼があればぜひお問い合わせください。
HPへ→研修のお問い合わせはこちらから
最後までお読みいただきありがとうございました!